リンクから商品をご購入いただくと、サイト運営の応援につながります(購入者さまのご負担は一切ありません)。
サーバー代や記事作成の励みに活用させていただきますので、ご理解いただけると嬉しいです。
詳細は 免責事項・利用規約・広告ポリシー をご確認ください。
こんにちは、信州どぼくまです。
今回は、現場でよく耳にする「段取り八分」という言葉について、私自身の実体験とともに、どう現場で活かしていくかを掘り下げてみたいと思います。
↓前回の記事はこちらです↓
【安全対策】熱中症対策の基本と現場での実践例|2025年法改正にも対応【実務-004】
↓こちらの記事も、現場を進めていくにあたって経験上便利だったグッズです。
【実務-006】現場監督が選ぶ!作業効率が上がるおすすめグッズ15選
【実務-007】現場代理人が常備しておきたい道具まとめ(車載装備編)
「段取り八分」とは、ただの格言じゃない
「段取り八分、仕事二分」とよく言いますが、これは単なる言葉の綾ではなく、現場では“本質”を突いた考え方です。
仕事の大部分は、実際に体を動かす前に終わっている。つまり、事前の準備や計画をどれだけ丁寧にやっておけるかが、工事のスムーズさと品質を左右します。
「当日現場に行ってから考える」はNG。逆に、前日にすべての段取りが終わっていれば、当日はスムーズに対応できます。
現場での段取りって、何を指すのか?
段取りといっても、「段取り表を作る」だけじゃありません。私が意識しているのは、次のようなポイントです:
- 工種ごとの作業フローを頭に入れる(掘削 → 路盤 → 舗装 など)
- 天気や搬入経路、交通規制の有無などを事前にチェック
- 協力業者と“言った・言わない”が起きないよう、口頭だけでなくメールやLINEなどでも確認
※協力会社に限らず公共工事では関係役所とのやり取りに“言った・言わない”が起きないよう
施工協議書・メールで記録を残します。
この記録は、自分自身や会社を守るためにも大事です。 - 仮設・機材・材料の搬入タイミングをすり合わせ
- 前工程の遅れ・変更があった場合のリスケジュール案も想定
「備えあれば憂いなし」は、まさに段取りのことです。
段取りが整っている現場は「楽」になる
一見、準備に手間をかけているように見えても、段取りがしっかりしている現場は本当に楽です。
- 朝礼での指示がスムーズになる
- 作業員が迷わず動ける
- 材料が足りない・届いてないといった混乱がない
- 最後の片づけが早い、定時で終わる
「今日、なんかスムーズだったな」という日こそ、段取りがきれいにハマった日です。
逆に、予定が詰まってる日に限って、段取り不足で大混乱になる…というのは、あるあるです。
段取りは“自分の中”だけじゃ意味がない
大事なのは、「自分だけが把握している状態」ではなく、現場の誰に聞かれても内容が共有されている状態を作ることです。
私はホワイトボードを活用したり、簡易な「本日の作業予定表」を紙1枚で配るようにしています。
また、初回の同種工事の写真帳をベースに「ここは毎回やる作業だな」とパターン化して段取りに組み込むのも有効です。
※毎回やる作業でも慢性化するとKY活動もおろそかになるので注意が必要です。
まとめ|段取り八分は、“手を抜かないための習慣”
段取りを制す者は現場を制す。そう断言できるほど、段取りは現場にとって重要なキーワードです。
- 前日に準備を終わらせるクセをつける
- 一歩先を見越して考える
- チームで段取りを共有する
こうした積み重ねが、結果として「今日はうまくいったな」「信頼される現場監督だな」という評価につながります。
今後は、「段取りリスト」や「1週間前にやること・前日にやることチェックリスト」など、より具体的な内容も紹介していく予定です。
次の記事の紹介です。
【実務-006】現場監督が選ぶ!作業効率が上がるおすすめグッズ15選
🟢 実務カテゴリの一覧はこちら
→ 【実務カテゴリTOPへ】

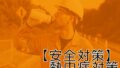

コメント