リンクから商品をご購入いただくと、サイト運営の応援につながります(購入者さまのご負担は一切ありません)。
サーバー代や記事作成の励みに活用させていただきますので、ご理解いただけると嬉しいです。
詳細は 免責事項・利用規約・広告ポリシー をご確認ください。
こんにちは、信州どぼくまです。
今回は工具・車両・実務レビューから少し離れて、アーク溶接資格について解説します。
↓前回の資格関連記事はこちらです↓
【資格-008】チェーンソーの選び方と現場カスタム|おすすめ機種と防護具レビュー
アーク溶接とは?
アーク溶接とは、電気のアーク放電を利用して金属を接合する方法です。
非常に高温のアーク熱を利用するため、鉄や鋼材をしっかり溶かして一体化させることができます。
- 電極として「溶接棒(被覆アーク溶接棒)」を使用
- 溶接中は数千℃の高温に達する
- 高電流を扱うため、感電や火傷のリスクがある
つまり、便利で強力な技術である一方で、正しい知識と安全管理がなければ非常に危険な作業です。
だからこそ「資格」が設けられています。
資格取得の流れ
私が資格を取得した際は、3日間の講習(座学+実技)でした。
1日目:安全衛生や基礎知識の座学
2日目:アーク溶接の基礎練習(ビードを引く練習など)
3日目:実技試験・学科試験
受講者は本当に幅広く、
- 普段から溶接を本業にしている溶接工の方
- 型枠作業など、必要なときだけ溶接する現場作業員
- 趣味やDIYレベルで「溶接に挑戦してみたい」方
と、さまざまなバックグラウンドを持つ人が集まっていました。
学んだことと印象
座学では「感電・火傷・有害ガス」といった危険性への理解が中心。
実技では、ひたすら溶接棒を溶かしながらアークを安定させる練習を繰り返しました。
正直、初めてのときは全然うまくできず、アークが飛ばずに棒を金属にくっつけてしまったり…。
ですが、講師や経験者の方に教わりながら徐々にコツを掴んでいけました。
資格取得のメリット
- 現場でアーク溶接を合法的に扱えるようになる
- 工事によっては「資格保有者が必須条件」になっている
- DIYや趣味レベルでも、安全知識を学んでから取り組める
「とりあえず溶接してみたい」ではなく、しっかり学んで資格を取ることが、安全かつ効率的に作業する第一歩だと実感しました。
まとめ|“危険だからこそ学ぶ”資格
アーク溶接は強力な技術ですが、一歩間違えれば重大事故につながる危険もあります。
だからこそ、
- 基礎知識と安全管理を学ぶ
- 資格を取得して正しく扱う
この2点が欠かせません。
現場作業員はもちろん、DIYで溶接にチャレンジしたい方にも、資格取得を強くおすすめします。
次の記事の紹介と、関連リンクです。
【資格-010】※リンク予定 自由研削といし特別教育|刃の交換にも資格が必要な理由
【工具-030】※リンク予定 溶接面(保護具)|目を守るために選びたい自動遮光面と私の失敗談
【工具-029】※リンク予定 スズキッド スターク120|小型アーク溶接機を試してみた感想
【工具-028】※リンク予定 アストロプロダクツ MIG-130-A|直流半自動溶接機を使ってみた感想
【工具-002】HiKOKI vs マキタ|現場で選ばれる電動工具メーカー比較とおすすめ機種
🟢 資格カテゴリの一覧はこちら
→ 【資格カテゴリTOPへ】
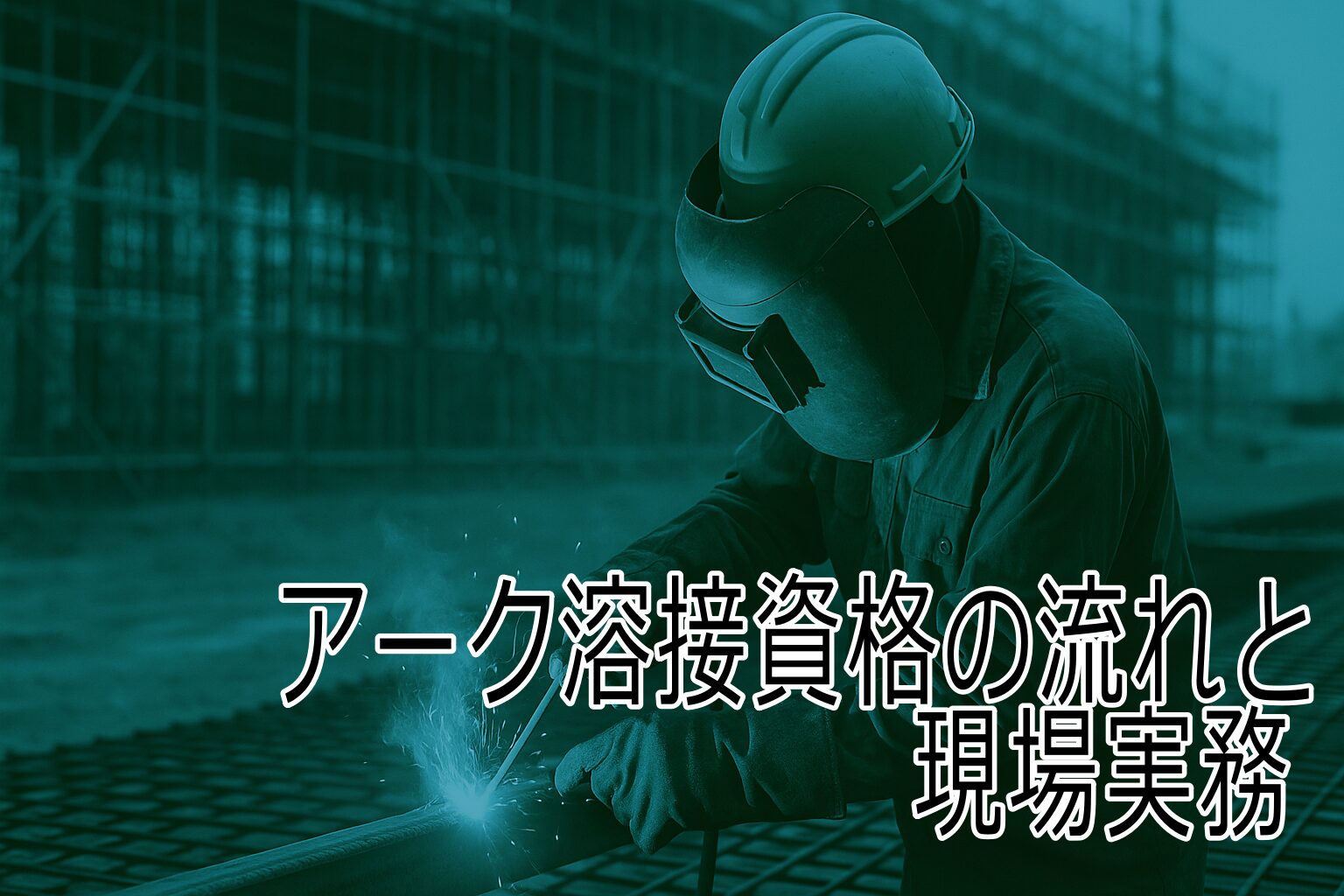


コメント